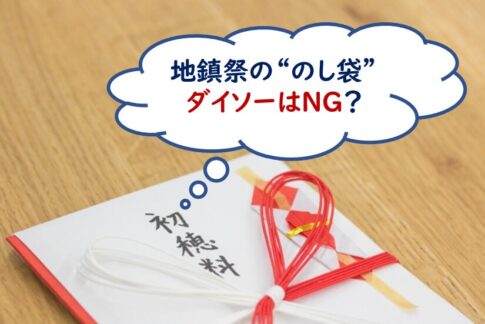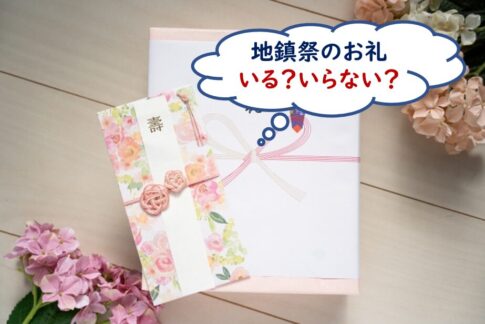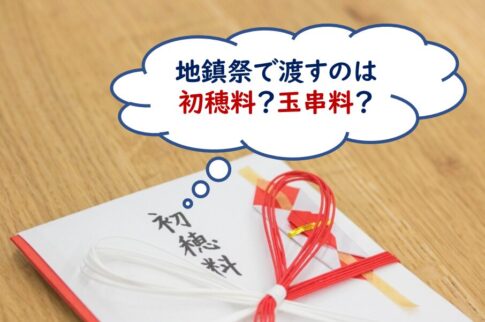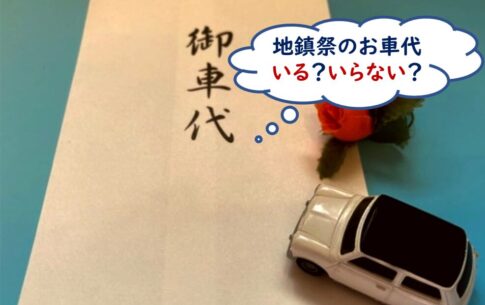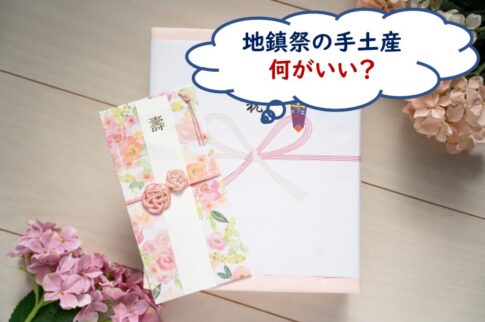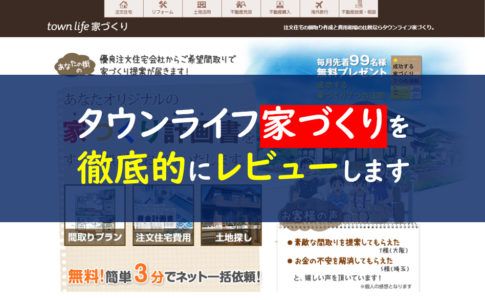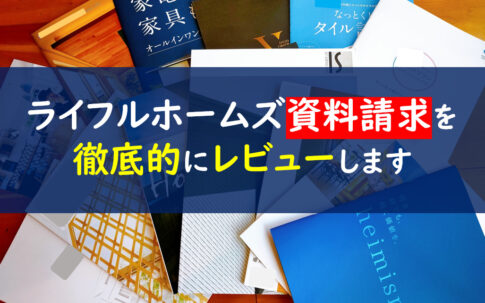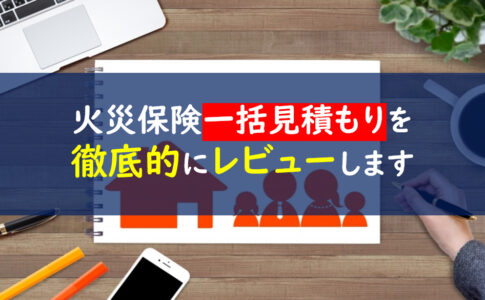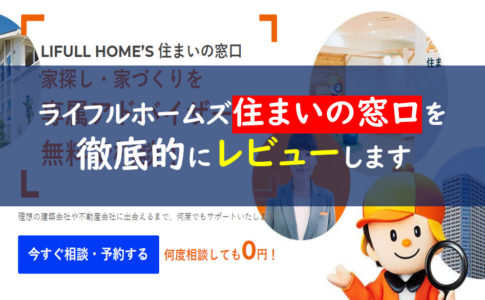「地鎮祭のお供え物って、どこで買ったらいいの…」
「お供え物セットとして、通販で購入できないのかしら…」
神様を迎える大事な地鎮祭で欠かせないのが「お供え物」。
私も「お供え物セット」を購入することで、無事に地鎮祭を執り行うことに成功しています。
地鎮祭の「お供え物」について、あなたに伝えたいことは3つ。
POINT
- 事前に予約すれば、近所のスーパーでも手に入る
- 乾物の用意には、通信サイトの利用がおすすめ
- 用意するのが難しいなら、神主や住宅メーカーに依頼
ただ、通販で「お供え物セット」を購入したために、トラブルに遭う人がいるのも事実…。
建築会社が教えてくれない、「お供え物」の真実に迫っていくことにします。

地鎮祭のお供え物はどこで買う?

地鎮祭のお供え物には、主に次の8つのアイテムが必要です。
横にスクロールできます⇒
| 清酒 | 清酒一升(1.8リットル) ※祝儀用の「のし紙」を付ける |
| お米 | お米一合(180cc) ※洗米しなくてもOK |
| 塩 | 塩一合 |
| 海のもの | 尾頭付きの魚(鯛など) |
| 乾物 | 昆布やスルメなど |
| 山のもの | 季節の果物 ※キノコ類でもOK |
| 野菜 | 地面の上にできるモノ (トマト・ナス・キュウリなど) 地面の下にできるモノ (大根・イモなど) |
| 水 | 水一合(180cc) ※水道水でもOK |
お供え物を1つの場所ですべて購入するのは難しいので、実際には様々な店を巡って集める必要があります。
- 清酒:酒屋・ネット
- お米・塩・水・山の幸・野菜:近所のスーパー
- 尾頭付きの鯛(生魚):魚屋
- 乾物:百貨店(デパート)・ネット
「尾頭付きの魚」はスーパーでも手に入りますが、事前に予約しておくのが安心です。
地鎮祭のお供え物は誰が用意する?

地鎮祭のお供え物は、施主が用意するのが古くからの慣習。
ただ、実際に揃えるのは大変なので、最近は「神主」や「住宅メーカー」で準備するケースが大半です。
個人で集めるのが難しい場合は、住宅メーカーの担当者に聞いてみてください。
地鎮祭を設営するための道具は「神主(施工業者)」が用意するのが通例です。
ちなみに、お供え物の準備にかかる費用は5000円~1万円ほど。
神主さんにお供え物を用意してもらう場合は、「お車代」と合わせて2万円を渡すのが相場となっています。
関連 【地鎮祭にお車代はいらない?】封筒の書き方はこれが正解!
乾物(するめ)は通販がおすすめ

お供え物の中で、特に準備が難しいのが「乾物」。
昆布・ワカメ・スルメイカ・しいたけ・寒天 など
神事で使えるような立派な乾物は、近所のスーパーではなかなか手に入りません。
デパートが近くにない場合は、楽天やamazonなどの通販サイトを利用するのがおすすめ。
通販サイトだと「のし付きの清酒」も簡単に手に入るので、一石二鳥ですよ!
お供え物で特に用意しにくいのが「乾物」。楽天やamazonではキャンペーン実施中なので、今が最大のチャンスですよ!
【まとめ】地鎮祭では服装や挨拶のマナーも
地鎮祭のお供え物についてまとめます。
POINT
- 事前に予約すれば、近所のスーパーでも手に入る
- 乾物の用意には、通信サイトの利用がおすすめ
- 用意するのが難しいなら、神主や住宅メーカーに依頼
最近では通信販売も始まり、以前よりお供え物の準備が楽に。
代わりに「服装」や「挨拶」で失敗する人が多いので、特に注意してください。